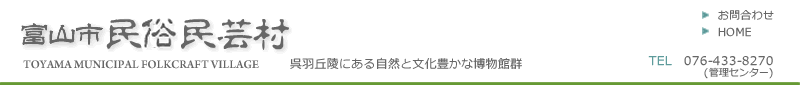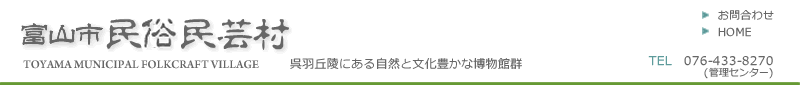売薬という商売の方法について、まず各家庭を訪ね、薬を先に預けて使用してもらいます。次に訪れた際(半年〜1年後)に使った分の薬代を支払ってもらい、未使用の薬を回収し、需要のある新しい薬を補充します。この方法を長く繰り返す商売です。よってこの販売システムは「先用後利」(用を先にし、利を後にする)と呼ばれます。
富山売薬は、江戸時代の初期、富山藩2代藩主前田正甫公の時代に始まるといわれています。その起源については、様々なことが考えられていますが、「反魂丹」という富山の代表的な薬も大きく関わっています。
江戸中期以降、全国的に富山売薬の販路が広がりました。富山藩は第一の産業として売薬を奨励し、税を納める仕組みを作って統制しました。売薬人は「示談」と呼ばれる守るべき取り決めを定め、互いに協力する体制をつくっていきました。
明治時代以降は、洋薬の影響や印紙税の賦課、そして幾度かの戦争により、商売が困難な時期もありましたが、昭和に向って発展していきました。現在でも富山では多くの人々が売薬(家庭薬配置業)に従事し、製薬も盛んに行われています。
現在、手作業での製薬はなくなり、行商のスタイルも変わり、道具などが失われつつあります。よって富山市では、かつて使用されていた売薬用具の散逸を防ぐため、多くの方々の協力を得て売薬に関する用具を収集してきました。
当館は、昭和56(1981)年に国重要民俗文化財の指定を受けた売薬関係資料846点を収蔵・展示するため、昭和59年(1984)に設置されました。現在では約6,000点余の資料を収蔵し、常設展や企画展でご紹介するとともに、売薬に関する資料を収集しています。
常設展示は、下記のように区分して展示し、富山の売薬についてご紹介しています。
◆ 富山売薬に関する史資料[「反魂丹旧記」ほか]
◆ 行商用具[柳行李、懸場帳など]
◆ 手作業で薬を作っていたときの製薬用具[薬研、下枡、薬袋など]
→丸薬作りの実際の様子を、映像でご覧いただけます。
◆ 売薬のおまけ・進物類[売薬版画、紙風船など]
◆ 信仰儀礼用具[神農像など]
それでは展示資料の中から、各々についてご紹介します。
◆行商用具
 |
売薬さんは、この柳行李に薬などを
入れて、行商に出掛けていました。
柳行李とは、薬のほか商売用具入れで、4〜5段の重ねられる箱です。売薬さんの代名詞とも言えます。
上の段からそれぞれ入っているものを挙げると、
1段目…筆記用具(帳面、筆入れなど)、印判、インク、
算盤他
2段目…みやげ品、チラシなど
3段目…回収した古い薬
4・5段目…これから配置する新しい薬
(5段目には高貴薬)
他にもこの行李には、使う人によって、それぞれ工夫されています。 |
◆製薬用具
 |
主に江戸時代は、売薬の商売をする人が自分で薬を作っていきました。
これらは、薬を作るための道具の一つです。
←これは「薬研」というものです。
どのように使ったものでしょうか? |
| |
|
 |
←これは「下枡」という道具で、扇型製丸機とも呼ばれます。
江戸時代後期に、富山の算学者が考案したものと言われています。
当館の映像でも使い方を紹介しています。
|
| |
|

|
薬は、今も昔も、たくさん種類があります。
腹薬、風邪薬、頭痛薬、目薬…。
古くは、万能薬と言われたものもあります。
薬袋もたくさん展示しています。
大きさや用途、デザインも様々です。 |
◆みやげ品・進物類
 |
富山の売薬では、みやげ品を配っていたことでも
よく知られています。
←この売薬版画が、みやげ品の始まりとされています。江戸時代末〜明治時代後期の代表的なみやげ品でした。
「代表的な売薬版画」
暦絵や歌舞伎の絵など、たくさんの種類の図柄があります。 |
| |
|
 |
明治後期以降は、薬の宣伝チラシなども多く配られました。
みやげ品としてよく知られる紙風船やゴム風船のほかにも、様々な種類のおまけがありました。
それらも展示しています。
どのようなものがあるでしょう。
|
|