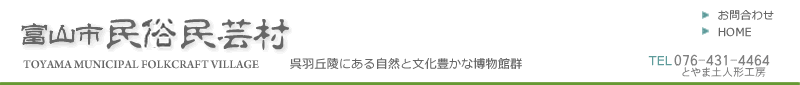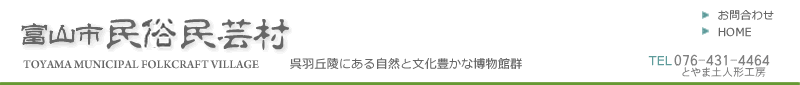由来・歴史 由来・歴史
嘉永年間(1848〜54)富山十代藩主前田利保が名古屋の陶工、加藤家の陶器職人であった広瀬秀信を富山に呼び、千歳御殿に窯を築いて千歳窯を作り、次いでその子・安次郎が陶器作りのかたわら天神臥牛を焼いて献上したのがとやま土人形の始まりです。
当時、城下には土人形屋は数軒ありましたが、広瀬家より技法を学んだ渡辺家(明治3〈1870〉年創業)だけが家業として伝統を守り続けてきました。
しかしながら、渡辺家の3代目信秀氏の後継者がいなかったために、富山市では昭和58(1983)年より渡辺信秀氏を講師として人形づくりの受講生を募り「とやま土人形伝承会」を結成しました。平成9(1997)年信秀氏高齢(83歳)のため、長年守り続けてきた土人形づくりに終止符を打ち、代々受け継がれてきた型・技法全ての仕事を「とやま土人形伝承会」に委ねました。現在は「伝承会」がこの伝承技法を後世に伝えるべく活動を続けております。
 特徴 特徴
とやま土人形は、とやまの産業、伝統、風俗を取り入れて、一つひとつ真心をこめた手づくりの伝統民芸品です。代表的なものとしては、学問の神様である「天神様」、桃の節句に飾られる「抱き雛」があります。
 |
 |
| バラエティ溢れる土人形・土鈴 |
桃の節句 |
|