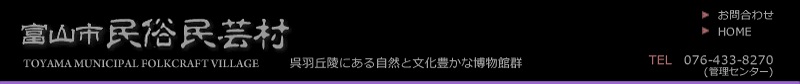 |
 |
 |
 |
 |
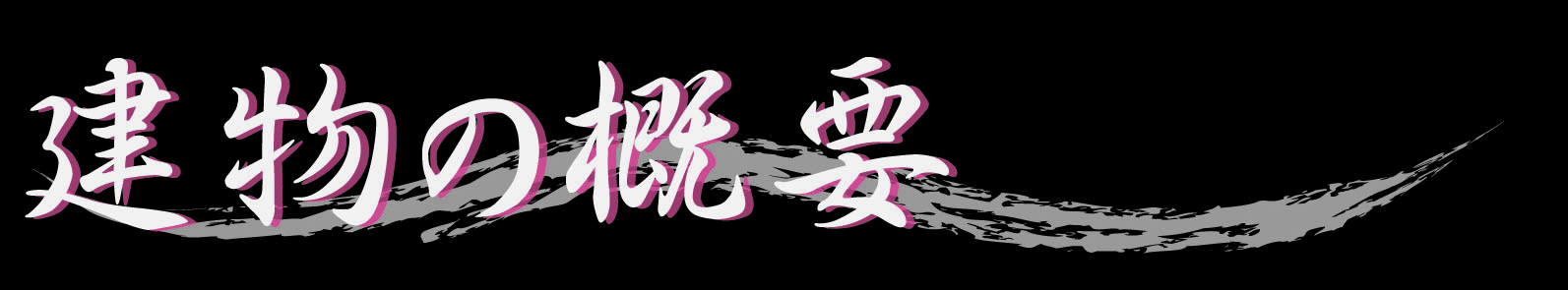 |
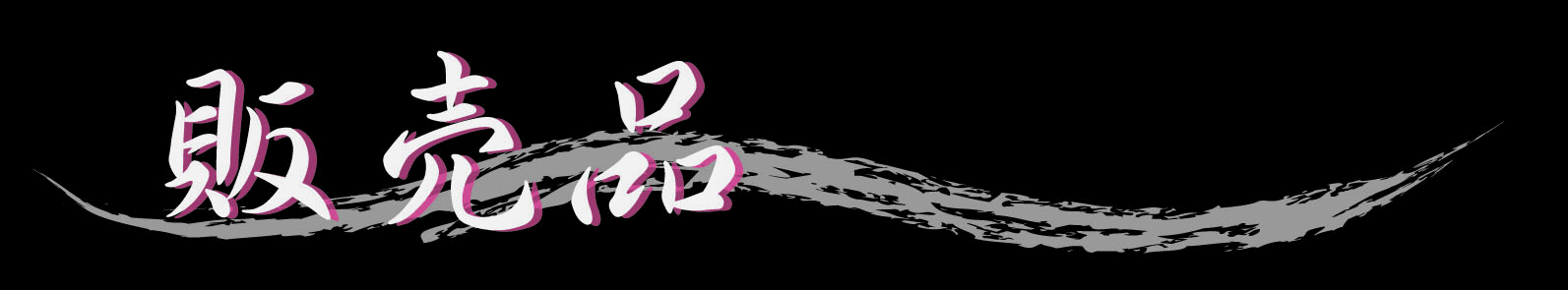 |
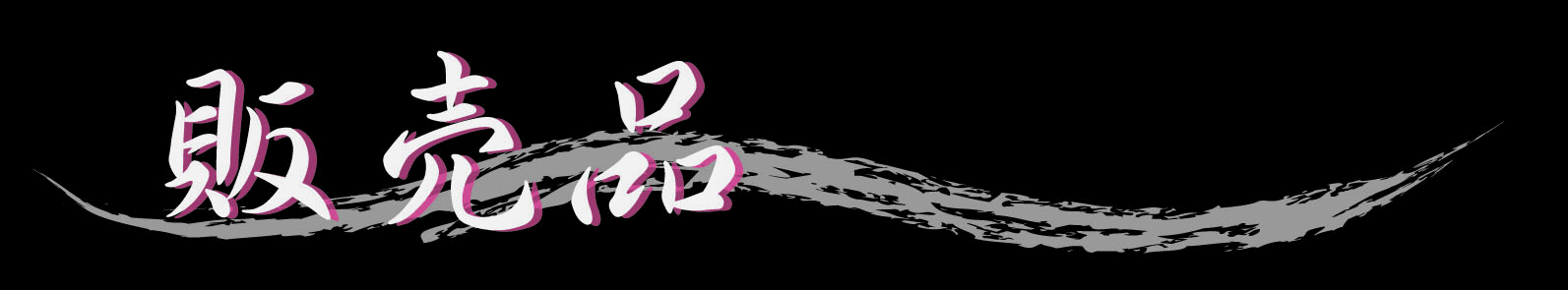 |
|
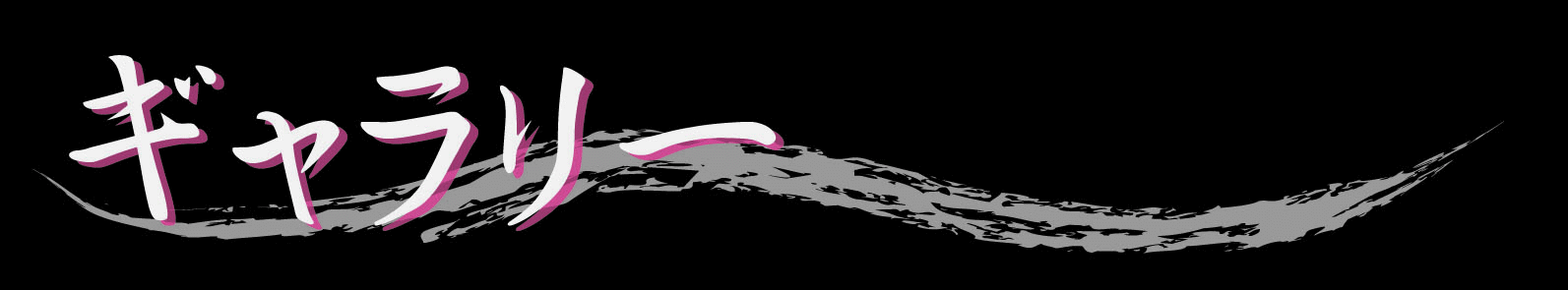 |
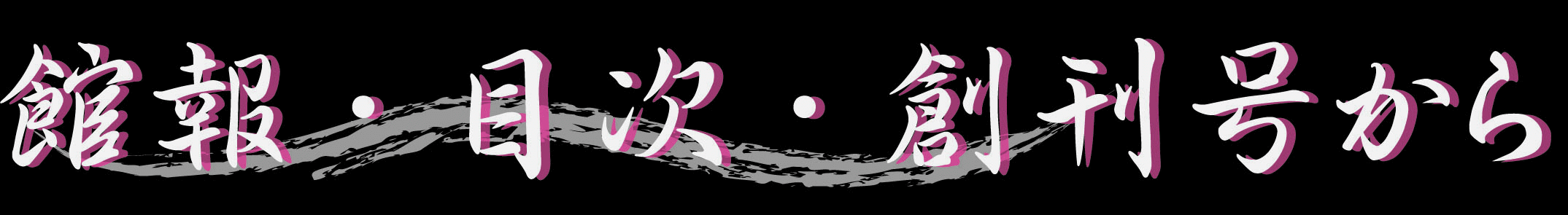 |
| |
|
|
|
 |
館報の創刊号からの目次を紹介いたします。
1冊500円
(※郵送での購入も可能ですので、ご希望の方はお問い合わせください。
電話番号 076-433-9215 ・・・送料別途) |
|
|
 |
|
|
| 創刊号 1991年 |
|
| 篁牛人について 牛人との出逢い(一) |
森田 和夫 |
| 篁牛人記念美術館と現代の建築について |
菊竹 清訓 |
| 篁牛人の芸術について |
河北 倫明 |
| 東西風景画の特性 |
山本 正男 |
| 日本水墨画の流れ(Ⅰ)~初期水墨画A~ |
木村 弘道 |
| 平成2年度事業報告 |
|
| 平成元年度事業報告 |
|
| 第2号 1992年 |
|
| 篁牛人について 牛人との出遇い(二) |
森田 和夫 |
| 人物画の流れ~東洋と西洋の比較より~ |
藤田 啓子 |
| 我が牛人 |
寺本 親平 |
| 牛人さんの書 |
宮崎 重美 |
| 画業 |
盤若 一郎 |
| 日本水墨画の流れ(Ⅱ)~初期水墨画B~ |
木村 弘道 |
| 平成3年度事業報告 |
|
| 平成4年度展覧会年間計画 |
|
| 第3号 1993年 |
|
| 飯塚琅玕斎を語る |
飯塚 小玕斎 |
| 濱谷白雨の人と芸術 |
定塚 武敏 |
| 異端の画家 篁牛人 |
宮崎 重美 |
| 孤高の画家 濱谷白雨 |
宮崎 重美 |
| 篁牛人について 牛人との牛人との出遇い(三) |
森田 和夫 |
| 日本水墨画の流れ(Ⅲ)~初期水墨画C~ |
木村 弘道 |
| 平成4年度事業報告 |
|
| 第4号 1994年 |
|
| 牛人を語る |
野島 清治 |
| 篁牛人について―白熱の季節― |
森田 和夫 |
| 日本水墨画の流れ(Ⅳ)~初期水墨画D~ |
木村 弘道 |
| 平成5年度事業報告 |
|
| 展示活動 |
|
| 特別展 石黒 連州展 |
|
| 特別展 芹沢 銈介展 |
|
| 第5号 1995年 |
|
| 近代工芸と氷見晃堂 |
山崎 達文 |
| ―YOSIOコレクション― インドネシアの手仕事 |
金守 世士夫 |
| 孤高の画家 村井 盈人のこと |
松原 敏 |
| 牛人美の世界と優しさ |
森田 和夫 |
| 日本水墨画の流れ(Ⅴ)~初期水墨画E~ 吉山明兆 |
木村 弘道 |
| 平成6年度事業報告 |
|
| 第6号 1996年 |
|
| 柳宗悦と民芸 |
尾久 彰三 |
| 日本民芸館について |
尾久 彰三 |
| 牛人の「女性」 |
森田 和夫 |
| 九谷焼(一)―春日山窯― |
木村 弘道 |
| 日本水墨画の流れ(Ⅴ)~室町時代の水墨画(一)~ |
木村 弘道 |
| 平成7年度事業報告 |
|
| 第7号 1997年 |
|
| 日本の文様について |
水木 省三 |
| 九谷焼(二)―若杉窯および吉田屋窯― |
木村 弘道 |
| 篁牛人 ―人と作品― |
木村 昌弘 |
| スーラの芸術(概論) |
佐久間 詔代 |
| 江戸期における花鳥画の特質について |
稲垣 里穂 |
| 平成8年度事業報告 |
|
| 第8号 1998年 |
|
| 中国の絵画における六法論 |
遠藤 光一 |
| 伝統の創生―津田左右吉による加賀水引折型細工の創始― |
山崎 達文 |
| 日本水墨画の流れ(6)~室町時代の水墨画(二)・周文~ |
木村 弘道 |
| 九谷焼(三) 九谷諸窯 |
木村 弘道 |
| ガラス造形におけるスタジオ概念の形成 |
柴田 純江 |
| アルフレッド・イーストと明治の日本 |
藤田 啓子 |
| 平成9年度事業報告 |
|
| 第9号 2000年 |
|
| 詩人の絵画 川柳人としての篁牛人 牛人論① |
野島 清治 |
| 西川祐信の雛型本に関する考察 |
白石 陽子 |
| 普賢影向図~成立に関する一考察~ |
和佐本 静代 |
| 一枚の売薬版画から |
坂森 幹浩 |
| 鶯谷窯(1)―陶工 原呉山― |
木村 弘道 |
| A.イーストとA.ベルソールの見た京都 |
藤田 啓子 |
| 事業報告 (平成10・11年度) |
|
| 第10号 2001年 |
|
| 「詩人の絵画 川柳人としての篁牛人」② |
|
| ―絵は願いをかくもの 川柳は願いを唄うもの― |
野島 清治 |
| 平田玉蘊―江戸期の女性画家の生涯― |
池田 明子 |
| 鶯谷窯(2)―陶工 鶯谷正平― |
木村 弘道 |
| 美術館 ―視線が交錯する場―についての試論 |
笠木 日南子 |
| アルフレッド・イーストと日光 |
藤田 啓子 |
| 罪深き男女の図像―「海と大地」から「アダムとエヴァ」へ― |
尾形 季和子 |
| 平成12年度事業報告 |
|
| 第11号 2002年 |
|
| 薩摩画壇について |
山下 廣幸 |
| 「このむら肩衝茶入」―利家が愛蔵し利常がお成茶会で使った幻の茶入― |
上坂 信子 |
| 鶯谷窯(3)―陶工 横萩一光― |
木村 弘道 |
| アートバトラー Vol.1 |
笠木 日南子 |
| 福音書記者図像研究の変遷 |
宮内 ふじ乃 |
| 「クレシェンツィ・アカデミー」について 開設時期の問題を中心として |
吉住 磨子 |
| 平成13年度事業報告 |
|
| 第12号 2003年 |
|
| 前田利家と茶道 |
上坂 信子 |
| 日本水墨画の流れ(7)~室町時代の水墨画(三)・周文~ |
木村 弘道 |
| 明治22年の日本の芸術 C・ドレッサーの寄贈品とA・イーストの批評に関連して |
藤田 啓子 |
| 平成14年度事業報告 |
|
| 第13号 2004年 |
|
| 近世肥前有田窯における色絵 相撲人形をめぐる一考察 |
坪内 広子 |
| 加賀・越中の楽焼(一)大樋焼 ―前田家文書の紹介― |
木村 弘道 |
| 学芸ノート 盤若一郎作品解説~盤若一郎と篁牛人展より~ |
| 『エブソムの競馬』試論 |
齋藤 直子 |
| イコノロジー研究再考―沖縄の民間信仰図像の解釈のために― |
尾形 希和子 |
| トーマス・ゲインズボロの《ハウスメイド》 |
藤田 啓子 |
| 平成15年度事業報告 |
|
| 第14号 2005年 |
|
| 加賀・越中の楽焼(二)竹亭焼 |
木村 弘道 |
| 作品紹介「金時と熊」 |
|
フェッラーラのバラッツオ・スキファノイアの「月暦の間」―
一解釈の試み― |
森山 陽介 |
| イーストとドレッサーの漆工芸観 |
藤田 啓子 |
| 平成16年度事業報告 |
|
| 第15号 2006年 |
|
| 南画史序説Ⅰ |
木村 弘道 |
| 作品紹介「西王母」 |
|
| カラヴァッジオ作『聖マタイの召命』衣装考 |
吉住 磨子 |
| 1867年頃のジャポネズリィとマネの二点の作品 |
藤田 啓子 |
| 平成16年度事業報告 |
|
| 第16号 2007年 |
|
| 南画の系譜 |
木村 弘道 |
| 「誰ヶ袖図屏風」にみる定型的図像とその継承―図様パターンBを一例として― |
中神 明夏 |
| 研究ノート 「『フィジオログス』と『動物誌』における象」 |
尾形 季和子 |
| 1860年代のホイッスラーとジャポネズリィ |
藤田 啓子 |
| 平成18年度事業報告 |
|
| 第17号 2009年 |
|
| 学芸ノート 篁牛人作品解説「愛蔵~牛人コレクション展」より |
木村 昌弘 |
| 学芸ノート 盤若一郎作品解説~盤若一郎と篁牛人展より~ |
田尻 佐千子 |
| 70年代のホイッスラーとジャポネズリィⅠ 母の肖像画を中心に |
藤田 啓子 |
| 平成19年度事業報告 |
|
| 平成20年度事業報告 |
|
| 第18号 2011年 |
|
富山における田植枠の特徴と地域的差異
―富山市域を中心に― |
能川 志保 |
70年代のホイッスラーとジャポネズリィⅡ
カーライフとレイランドの肖像を中心に |
藤田 啓子 |
| 平成21年度事業報告 |
|
| 第19号 2012年 |
|
天神飾りは江戸から伝わった!?
―崇める富山、遊ぶ石川― |
大門 哲 |
| 富山と天神信仰 |
布村 徹 |
| 旧レイランド邸食堂 「孔雀の間」Ⅰ |
藤田 啓子 |
| 事業報告 |
|
| 第20号 2013年 |
|
語り伝えよう 富山の民話
いろりを囲むおはなし 第二集 |
|
|
|
| →篁牛人記念美術館TOPへ |
| |
|
| | 民俗民芸村とは | 展示情報 | 催し情報 | ご利用案内 | 交通案内 | 年間スケジュール | 周辺のみどころ | 学校関係者の方へ | HOME | |
Copyright (C) 2011 Toyamashi Minzokumingeimura.All Rights Reserved.
当サイトの内容・画像についての無断転載は禁じられています。 |
富山市民俗民芸村
管理センター
〒930-0881
富山市安養坊1118-1
TEL:076-433-8270
FAX:076-433-8370
E-mail:mingeikanri-01(at)city.toyama.lg.jp
※(at)を@に置き換えてください。  |
| |
|
|
|