| ←博物館だよりINDEXへ戻る |
| 第三十五号 平成11年11月30日 |
|
| 『富山名所 光厳寺と大法寺』 |
 |
| 富山名所を描いた色刷版画で、明治42年に発行されました。 これはその内、光厳寺(こうごんじ)(曹洞宗)と大法寺(だいほうじ)(日蓮宗)を描いたものです。共に江戸時代には富山城下の南東隅の寺町に属していました。両寺は富山藩主の菩提寺です。菩提寺が2寺あるのには理由があります。初代利次(としつぐ)は光厳寺を藩主の菩提寺と決めましたが、2代藩主正甫(まさとし)が日蓮宗に改宗してしまったのです。この時、藩では混乱を避けるため、藩主の宗門を1代交代とすることにしました。そのため、富山藩主の菩提寺は、光厳寺と大法寺の2寺となったのです。 両寺は広大な境内を持ち、境内には立派な堂宇が建ち並んでいました。しかし、共に富山大空襲の際に、寺宝や文書とともに焼失してしまいました。その後の区画整理に伴って、敷地は縮小しましたが、由緒ある寺院として現在に至ります。 この版画から、明治の頃の両寺の壮大な様子が偲ばれます。境内の雪景色はさぞ美しかったことでしょう。 |
|
||||
交通の要所 新庄を歩く ―武将・旅人・泥流・鉱石… みんな新庄を通っていった― |
|
| 1 新庄城をめぐる戦国物語 |
| 現在の新庄小学校が新庄城跡で、古くは「御屋敷山」と呼ばれた小高い丘でした。また、昔は本道や小道のほかは泥田で、薄(すすき)や葦などが生い茂り、更には東に常願寺(じょうがんじ)川、西にはその支流である荒川が流れる要害の地でした。交通の要衝であることから、早くから軍事上の拠点として重視されたため、新庄をめぐる戦いが何度も行われました。 |
| 【新庄城址】川や泥田に囲まれた要害で、上杉方や佐々(さっさ)方などの拠点となった 【荒川古戦場・地蔵堂東坂口古戦場・尻垂坂(しりたれざか)古戦場】 【正願寺】尻垂坂古戦場で、上杉謙信が首実検した後、敵の首を埋めたところ 【綾田の稲荷神社】上杉侵攻の頃、兵火を被る。焼けた榎の洞穴から御神体を発見 【覚性寺】上杉謙信の一向一揆征伐の兵戈に見舞われた 【橋宮神明宮】新庄城主三輪飛騨守長職・轡田備後守が崇敬 【新川神社】轡田(くつわだ)備後守が新庄在城の頃、廃れていた社を再興 【全福寺】新庄城主轡田備後守の祈願所として建立 【宝洞寺】秘仏千手観音菩薩は、轡田備後守の守本尊であったとの伝承 |
 板石塔婆 新庄城址より発掘 五輪図形を刻んである |
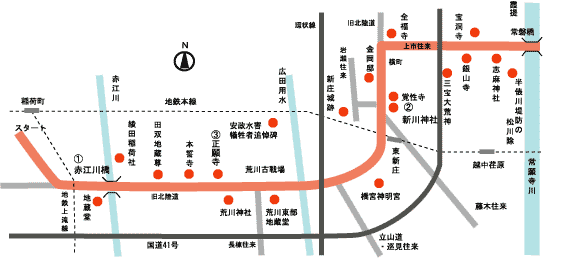 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 赤江川橋 | ||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2 新川神社 | ||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3 薄(すすき)地蔵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正願寺前。尻垂坂の合戦後、謙信が首実検し、その首を埋めた穴に自然石の塔を立てたのが起こり。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 宿駅の賑わい〜交通の要所〜 |
| 北陸唯一の幹線道路である北陸道が通る新庄は、元禄9年に馬継宿(うまつぎしゅく)と定められてからは小規模ながら宿駅(しゅくえき)として発達しました。更にこの地は、上市(かみいち)往来や岩瀬往来、立山道が分岐する交通の要所でもあります。また、富山・加賀藩境に近いことから、加賀藩領新川支配の拠点の一つでした。 |
| 【赤江川橋】富山と加賀の藩境で、両藩の折半で橋が架けられた 【本誓寺】売薬行商人の女殺しの伝説を伝えるムクの老樹がある 【立山道・巡見往来】立山への参詣路、巡見上使の進路 【上市往来】大岩参詣客で賑わう 【道標(全福寺前)】上市往来との分岐点 【長棟(ながと)往来・二松往来】 【岩瀬往来】東岩瀬へ |
 |
| 道標 |
| 3 安政大洪水の被害 |
| 安政5年の大地震により大鳶山・小鳶山(おおとんびやま・ことんびやま)が崩壊しました。その二次災害である大洪水は各地を襲い、遂には新庄の地にまで押し寄せました。大量の土石流のため、川は埋まり、丘は平地と化し、人々は移転を余儀なくされたのです。しかし、その反面、痩せた土地に肥沃な泥が流れ込み美田と化したり、流れてきた大石を利用して多くの名石工を輩出するという恩恵もありました。 |
| 【安政水害犠牲者追悼碑】作業中に溺死した関係者追悼 【田双の地蔵尊】大洪水で立山より流出埋没したものを堀出し安置した 【銀山寺・宝洞寺】大洪水により移転 |
 |
| 安政の大洪水以外でも、常願寺川との関係を示すものに、新庄の霞提・松川除(かすみてい・まつかわよけ)などがあります。また、新川神社は近郷の農民から常願寺川の守り神・水神としてあがめられてきました。 | 安政水害犠牲者追悼碑 |
| 4 鉱山支配と新庄 |
| 新庄からは、亀谷(かめがい)銀山や長棟(ながと)鉱山への道も開かれています。寛文の頃には新庄に、越中七金山(かねやま)を支配した役所である金山裁許(かなやまさいきょ)が設けられました。新庄銀座という地名は、新庄金山裁許の跡と考えられます。また、亀谷銀山衰退の後、同地より新庄へ移った寺院もあります。 |
| 【正願寺・銀山寺】亀谷(かめがい)銀山より新庄へ移転 【立山道】上滝で常願寺川を渡らずに東進すれば亀谷銀山に達する 【長棟往来】二松から東進すると長棟(ながと)鉱山に達する 【山田秀蔵顕彰碑】加賀藩に仕え、長棟・亀谷の二鉱山の事務を執った |
 |
| 正願寺 |
| ▲UP |
| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:河西奈津子) |