| ←博物館だよりINDEXへ戻る |
| 第十一号 平成9年12月11日 |
|
|||||
| 『 宝 く じ 』 |
 |
| 第一回宝籤 |
 |
| 富山県復興宝籤 |
| 宝くじはいつ頃から発行されているかご存じですか?江戸時代には富籤(とみくじ)が出され、明治以降も同じような性格の債券が発行され続けましたが、「宝くじ」というものが発売されるのは、終戦直後の昭和20年の10月のことです。価格は1枚10円で、一等賞金は10万円でした。また、当時の物不足を反映して賞金のほかに副賞として純綿キャラコ二反が賞品としてついていました。また、この政府くじのほかにも、地方くじが翌21年以降各地で発売されました。当県では昭和22年に「富山県復興宝籤(とやまけんふっこうたからくじ)」が発売されています。一等賞金は1万円、一等賞品は自転車用タイヤ及チューブ1組でした。ちなみに翌年の第二回復興宝籤の特賞品は自転車1台となっています。 |
 |
当館では年に1〜2回「歴史探訪ツアー〜富山を歩く」と題して、富山市内の古い道を歴史的解説を聞きながら歩く会を開催しています。今年度は去る11月15日に浜黒崎方面の浜街道を歩きました。浜街道とは中世・近世における越中海岸沿いの街道のことをいいます。またこのルートは北陸道の、そして加賀藩主の往還道の一つでもあります。今号ではそのルートの見所をご紹介します。参加されなかった方も1度歩いてみませんか? |
|
| 三文塚前での解説風景 |
| このルートは中世越後の上杉氏の侵攻経路となっていました。そのため要衝であったこの地には、大村城を本拠とした轡田(くつわだ)氏がいました。轡田氏は初めは守護代の神保氏に従っていましたが、度々の越後勢の侵攻により、上杉方に付きつ離れつしていたのです。天正6年に上杉謙信没後は轡田豊後(くつわだぶんご)が居城しましたが、後に上杉方に攻め滅ぼされました。そこでこの地には轡田氏に関する伝説や遺構が多く残ります。 |
| A 大村城跡 戦国時代の轡田氏の居城。現在は曹洞宗瑞円寺の境内となっており、堀や土塁の跡が残ります。 |
 |
| B 日方江(ひかたえ)城跡 天正年間の大村城の出城でした。江上重左衛門が居城としていましたが、後に佐々成政に追われたと言われます。現在は了照寺の境内となっています。 |
| 精霊塚 |
| C 泉福寺(せんぷくじ) 高野山真言宗。大村城主轡田豊後が上杉謙信に敗れたのち剃髪して住僧になったと伝えられます。 |
 |
| くまの地蔵 |
| D 炊きさしの宮跡 かつては八幡宮があり、天正6年に上杉勢が大村城攻撃のため戦勝祈願をしました。その後に境内で朝食の支度をしていたところ、突然の攻撃命令により、飯を炊きさしのまま出陣したといいます。 |
| E そうけ塚(三文塚) 天正6年に上杉勢が大村城攻略にあたり、城の内外を望見するために、近村住民に“そうけに一杯の土砂を持ってきた者には銭三文を与える”と命じたところ、一夜のうちに大丘が築かれたといいます。 |
| F 精霊塚 天正6年の上杉勢侵攻によって大村城は落城しました。その時の戦死者を葬った塚といわれます。城からの抜け穴の跡もみられます。 |
| G くまの地蔵 松並木に現れた魔物を轡田豊後が退治したという伝説が残ります。 |
| 江戸時代には加賀藩主である前田氏の往還道(おうかんどう)となっていました。往還道とは藩主が参勤交替の折に通った道です。 |
| H 街道松(往還松(おうかんまつ)) 慶長6年に加賀藩主前田利長(としなが)が、美観と積雪時の目印にするために往還路に黒松を植樹しました。戦時中に多く伐採されています。昭和40年に県天然記念物に指定されました。 |
| I 旧街道筋遺構 旧街道筋と現在の富山−魚津線は全てが一致するわけではありません。往還松(指定番号4)の付近や家々の裏道に旧道の名残がみられます。そうけ塚の祠は旧道を望んでつくられています。 |
 |
| 大正12年頃の並木松 |
| J 古志(こし)の松原記念碑 昭和7年に帝国美術院長正木直彦氏が来富の折、この松原の美しさを激賞し、「古志(こし)の松原」と名付けました。 |
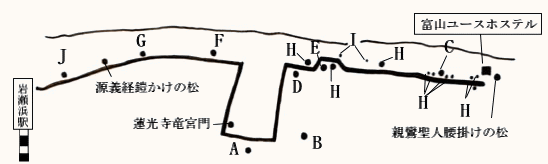 |
| 各所には詳細な解説看板もありますので、歩いて又は自転車に乗って辿ってみて下さい。戦国時代の轡田氏と江戸時代加賀藩主の往還松を訪ねるコースをご紹介いたしました。お天気のよい休日に頭と体を鍛えるためにいかがですか? 富山ユースホステル出発 岩瀬浜駅まで3時間コース |
| ▲UP |
| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |