| ←博物館だよりINDEXへ戻る |
| 第伍号 平成9年6月4日 |
|
| 『杣田青貝細工 鐔(そまだあおがいざいく つば)』 |
 |
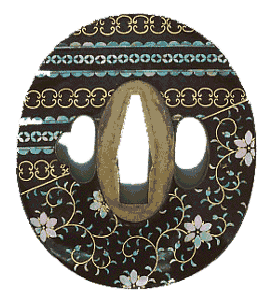 |
| 鐔(つば)とは刀装具(とうそうぐ)のひとつで、柄(つか)を握る手を刃から守るためにつけられるものです。 | 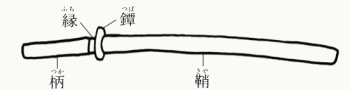 |
| この青貝細工の鐔には両面に模様があります。一面は、鳳凰文(ほうおうもん)など3種類が、もう一面は草花文など2種類が、線で区切って描かれています。写真では片面ずつしか見えませんが、2枚の鐔の模様は裏表それぞれ対になっています。また縁(ふち)も揃いの模様のものがあります。 青貝細工は、漆を塗った素地に青貝をはめ込み、その上から再び漆を塗り、その後青貝が見えるように研ぎ出していく、という方法で作られます。 |
| 富山藩では、2代藩主前田正甫(まえだまさとし)が青貝細工師の杣田清輔(そまだきよすけ)を招き入れました。それから代々杣田氏が青貝細工技術を受け継ぎ、作品を製作するようになりました。 青貝細工はたいへん珍重され、藩の進物として用いられたようです。この鐔も贈答用に作られたものでしょうか。 限られた面の中に細かい模様が見事に表現され、杣田氏の技術の高さを伝えています。 |
| 現在の富山城址公園は、富山城のあった場所を示していますが、江戸時代の富山城の広さを表すものではありません。さて、その大きさはどれほどだったのでしょうか。 | |
| 富山藩の城となった富山城は、初代藩主前田利次(まえだとしつぐ)によって寛文(かんぶん)元年(1661)以降整備されました。その後 明治時代まで、その城域はほとんど変化していません。 | |
| 下に「富山城絵図」を挙げます。この絵図は、嘉永7年(1854)に作成されたもの(写し、部分)ですが、江戸時代の富山城はこのような形をしていました。 | |
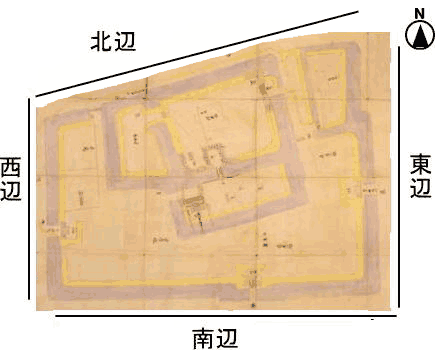 |
| 下の図も参考にして見てください。 |
| 江戸時代の富山城の全体の大きさは、堀を含めると、 (1間=1.818mで計算しています。以下同様) 北辺 280間=およそ509m 東辺 254間=およそ462m 南辺 326間=およそ593m 西辺 170間=およそ309m となります。(面積を計算してみてください!) |
| 富山城のそれぞれの曲輪(くるわ)の名称と、建物の様子を大まかに挙げます。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| (上記の番号は図中の番号と一致します。) 曲輪(くるわ)の中の建物は随時変化しており、江戸時代を通して確定はしていません。 |
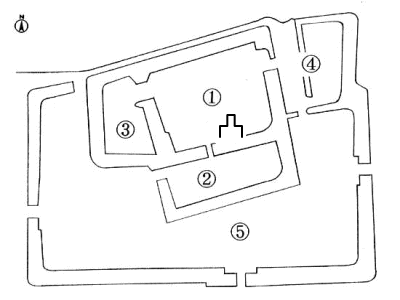 |
| 現在の城址公園はほぼ本丸と西出丸にあたります。 本丸と西出丸の大きさは、以下のようになります。(堀を含めない) ・本丸 北辺 85間=およそ155m ・西出丸 北辺 36間=およそ65m 南辺 83間=およそ151m 南辺 48間=およそ87m 東辺 80間=およそ145m 東辺 60間=およそ109m 西辺 73間=およそ133m 西辺 53間=およそ96m これを合わせると現在の公園の範囲となります。辺だけを比べても、江戸時代の富山城は現在の公園よりもはるかに大きいことがわかると思います。 *この富山市郷土博物館は、本丸の入り口付近の石垣の上に建てられたものです。(図に |
| この富山市郷土博物館はお城のかたちをしています。「この博物館は天守閣を模したものですか?」とよく聞かれます。実際には、富山城に天守閣はありませんでした。 城の中心は本丸にあった本丸御殿です。現在の公園内の芝生広場にあたる場所に建てられていました。 下の図で江戸時代初期の御殿の形を示します。(「利興公御代富山御本丸御絵図」富山県立図書館蔵を参考)本丸御殿は藩政を執る場所であり、また藩主が生活する場でもあったようです。 |
|
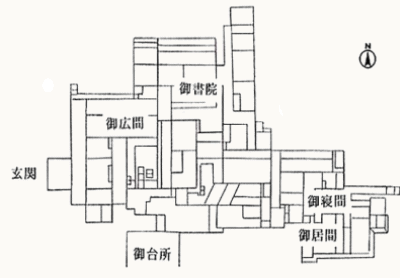 |
| しかし、この本丸御殿も正徳4年(1714)御殿内からの出火で焼失してしまいます。その後 御殿の機能は本丸以外に置かれたりしていましたが、天保3年(1832)に本丸御殿の修築許可が出ました。この時建てられた本丸御殿が、明治まで残っていました(写真)。この御殿は、廃藩置県後 県庁として利用されたのですが、資料があまり残っていません。全景や内部の様子はどうなっていたのでしょうか。きっと富山藩政時代の名残を止めるものだったのでしょう。 |  |
| ▲UP |
| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |