| ←博物館だよりINDEXへ戻る |
| 第十七号 平成10年6月23日 |
|
| 特別企画 |
| 富山城の遺構を訪ねて |
 |
| 今回は富山城の中に入らなくても見ることができる、富山城に関連する歴史的遺構をご紹介したいと思います。 まず第一は城址公園内に残る石垣と堀です。 公園内に残る当時の唯一の遺構です。 この石垣の上には、現在のような天守閣が建っていたわけではありません。 本来は本丸に続く鉄御門(くろがねごもん)があった跡なのです。 堀は、江戸時代には本丸・二の丸・三の丸をそれぞれ囲んでいたのですが、徐々に埋め立てられ、 現在はこの博物館の南側に僅かに残るのみです。 上の写真は明治時代後期の城址の様子を写したものです。 |
| まずは堀の石垣と同様、石製であったために、大火や戦災にも耐えて現在まで残った貴重な遺構をご紹介します。 |
| 現在、郷土博物館の入り口横にある2つの石が、富山城の二階櫓御門(にかいやぐらごもん)の礎石です。 江戸時代には二の丸の北西隅に、二階建ての櫓御門がありました。 この門は明治時代になっても残っており、小学校(俛焉(べんえん)小学校ー現在の富山市立総曲輪(そうがわ)小学校の前身)の校舎として利用されました。 しかし明治16年頃には解体されてしまいます。 その後この跡地は様々な施設に利用されましたが、現在では国際会議場の建設が進められています。 <現在:城址公園内(富山市本丸)> |
 |
| この場所は近世以来、小船をつないで板を渡して橋とした舟橋が架かっていた場所で、明治16年に木橋(神通橋)に架け変えられました。 明治16年頃に二の丸にあった二階櫓門が撤去されていることから、これと時期を同じくして二の丸が完全に解体されたと思われます。 このことから二の丸が解体された際に、ちょうど架け変えられた神通橋の土台に転用されたのではないかと考えられるのです。 石の様子も現在城址に残る石垣によく似ています。 <現在:松川に架かる舟橋の下(富山市丸の内)> |
 |
| 境内を散策すると、拝殿前の平な地面に埋もれた石橋に気付きます。 この不思議な石橋は富山城の正門である大手門前に架かっていた橋の部材を使用したものだといわれます。 於保多神社は天神様を祀(まつ)る神社です。 江戸時代には富山藩主前田家の氏神として、保護されていました。 <現在:於保多神社 拝殿の前(富山市於保多(おほた)町)> |
 |
| さて次に木造の遺構をご紹介しましょう。 富山城内にあった門で移築されて残っているものは1件だけですが、家臣の屋敷の門は2件残っています。 安政・文久年間の火事以降に建てられ、明治以降に郊外に移築されたため、戦災にも遭わずに現在まで残った貴重な木造遺構です。 |
| 富山の町は江戸から明治に至るまで大火が多いところでした。 その上、昭和20年に大空襲に遭っていることから、古い遺構はわずかしか残っていません。 |
 |
千歳御殿は、富山10代藩主前田利保(まえだとしやす)の隠居所として、嘉永(かえい)2年(1849)東出丸(ひがしのでまる)に建てられました。 能舞台も含む、大変豪華な御殿でしたが、安政(あんせい)2年(1855)の大火事で焼失してしまいます。 この門は、その後再建された御殿のものと考えられます。 <現在:赤祖父(あかそふ)家(個人宅)所有(富山市米田)> |
 |
前田家の古くからの家臣で、富田弥五作という人物がいました。 この富田家を文政(ぶんせい)10年(1827)に継いだのが富田兵部(とみたひょうぶ)です。 嘉永(かえい)元年(1848)に家老となり、12代藩主前田利声(まえだとしかた)に仕えました。 安政年間の富山城下の地図には、大手門のすぐ南の西側一軒目が兵部の屋敷と記されています。 この屋敷の門でしょうか。 向かって左手が番所、右手が武器庫だったそうです。 <現在:中田家(個人宅)所有(富山市本郷町)> |

|
山田嘉膳(やまだかぜん)(1805〜1864)は柳川藩(福岡県)の人でしたが、富山藩家臣の養子となり、安政6年(1859)富山藩家老になりました。 この頃富山藩では加賀藩の政治介入が始まり、これに反発した家老たちが嘉膳を家老に任じたのです。嘉膳は加賀藩との摩擦を少なくし、善政を行おうと努力しました。 しかし、家臣の中でも入江民部(いりえみんぶ)の一派は、嘉膳に反発していました。 やがて嘉膳は元治(げんじ)元年(1864)城内三の丸で、入江一派の島田勝摩(しまだかつま)に暗殺されてしまいます。 嘉膳の屋敷は大手門のすぐ南にありました。 <現在:浄土真宗 教順寺(きょうじゅんじ) 所有(富山市塚原)> |
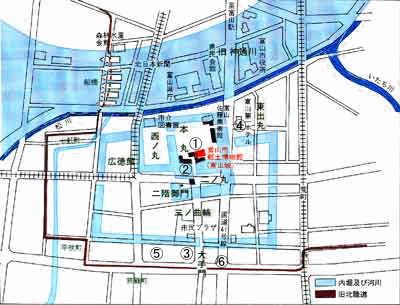 |
| 多くの災害をくぐり抜けて残ってきた遺物たち。これらが、当時どこにあったものかを上の地図中に表しました(番号は本文中の番号に対応します) 離れ離れになった遺物たちを訪ねてみて下さい。 |
| ▲UP |
| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心 河西奈津子) |