富山城で使用される築石に6種類の割り方があることは、富山城の割石技術(5)石を割る2分割方法の通りです。解体調査によって築石の割り方だけではなく、割る際に順序があることも石に残る矢穴痕からわかってきました。 |
二分割・四分割には小面→面と大面→小面の順で割る2種類の方法があります(図1)。 |
| |
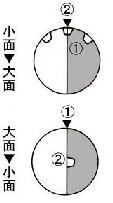 |
 |
| 二分割 |
四分割 |
|
| 図1 模式図 |
二分割 |
【小面→大面の順で割る場合】 |
| 1. |
石を輪切りにするように片端に矢穴をあけて割り、小面となる平面を作ります。 |
| 2. |
石の長い方に矢穴をあけて割る(大面ができる)と2つの築石が確保できます。割られた石には自然面から入れた矢穴痕が2箇所に残ります。 |
|
【大面→小面の順で割る場合】 |
| 1. |
石の長い方に矢穴をあけて割り、大面となる平面を作ります。 |
|
| 2. |
割面に矢穴をあけて割り、半月形の小面を作ります。石には自然面から入れた矢 穴痕と割面から入れた矢穴痕が残ることになります。 |
|
ただし、小面を作る方法には他に
| A. |
ゲンノウで小割りする方法 |
| B. |
割らずにそのまま使う方法 |
が認められます。これらは作業工程を省略化した ものと考えられます。 |
 |
 |
二分割
【大面→小面の順で割る場合】
1.段階 |
四分割
【大面→小面の順で割る場合】
2.段階 |
|
四分割A |
【小面→大面の順で割る場合】 |
| 1. |
石を輪切りにするように片端に矢穴をあけて割り、小面となる平面を作ります。 |
| 2. |
石の長い方に矢穴をあけて割る(大面ができる)と2つの築石が確保できます。 |
| 3. |
割面を上にし、長い方に矢穴をあけて割ります。自然面から2箇所+割面から1箇所・割面から1箇所矢穴痕の残る石が各2個できます。 |
|
【大面→小面の順で割る場合】 |
| 1. |
石の長い方に矢穴をあけて割り、大面となる平面を作ります。 |
| 2. |
割面を上にし、再度長い方に矢穴をあけて割ります。 |
| 3. |
割面に矢穴をあけて割り、扇形の小面を作ります。自然面から1箇所+割面から2箇所・割面から2箇所矢穴痕の残る石が各2個できます。 |
|
|
| 石割りは、築石を納めるまでの期間・割る石の大きさや状態・職人の好みなどが混在し、その時々で変化するものと考えられます。 |
| (鍋谷) |





