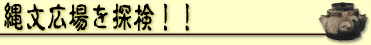 |
| |
|
 竪穴住居 竪穴住居 
|
 |
| 縄文時代の家 |
縄文時代の竪穴住居の屋根は、木で骨組みを作っていたため腐ってしまい、発掘調査をしてもなかなかその構造を確認することはできませんでした。
近年、小矢部市桜町遺跡で竪穴住居の柱がそのまま発見されたり、火事で焼けた住居の発掘で、炭になった柱や垂木が発見されたりして、次第に住居の屋根の構造がわかるようになりました。 |
| |
| 屋根に土をかぶせた住居 |
詳細な研究の結果、縄文時代の竪穴住居の屋根には土がかぶせられていたということが明らかにされました。これまで竪穴住居は、かやなどで屋根を葺いた草屋根の建物と考えていましたので、この研究は画期的なものでした。
北代遺跡で復元した土屋根の竪穴住居は、岩手県一戸町御所野遺跡、北海道虻田町入江貝塚に次いで全国で3例目の復元となりました。高床建物と土屋根住居をともに復元して集落の形で整備したのは国内初めてのことでした。 |
| |
| 住居の住み心地はどうだったの? |
住居の内部は、そのままだと湿度が90%以上もあり、とても住めたものではありません。
柱などの木も腐りやすく、すぐクモが巣を張ったりします。これを防ぐため、炉で火を焚くと、湿度が60%から70%まで下がりやや過ごしやすくなります。
その煙は、木に虫がついたりクモやカビの発生を食い止める「くんじょう」効果を持っています。おそらく縄文人もこのような工夫をしていたことでしょう。
また住居の中の温度は、極寒期をのぞき、ほぼ15度から20度で一定しています。特に真夏の昼間は、外気温より10度くらい低くなり、暑さをしのぐにはもってこいの環境となります。
このような土屋根住居の特性を縄文人はうまく利用して、すごしやすい住環境を整えていたと考えられます。 |
| |
  |