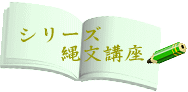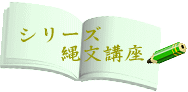| |
撽暥帪戙拞婜偐傜屻婜(崱偐傜栺5000偐傜4000擭慜乯偵棳峴偟偨憰忺昳偺堦偮偵忺傝嬍偑偁傝傑偡丅僸僗僀側偳偺愇傗噫噙側偳傪壛岺偟偰丄儁儞僟儞僩傗僱僢僋儗僗側偳偵梡偄偰偄傑偟偨丅
杒戙堚愓偱偼丄挿偝14cm傕偁傞崙撪桳悢偺戝偒偝偺戝庫偺傎偐丄岡嬍傗彫嬍側偳丄僸僗僀惢偺偝傑偞傑側忺傝嬍偑尒偮偐偭偰偄傑偡丅偙偺傎偐丄嶌傝偐偗偺偐偗傜傕尒偮偐偭偰偍傝丄杒戙堚愓偱僸僗僀偺嬍偮偔傝傪峴偭偰偄偨偲峫偊傜傟傑偡丅 |
 |
|
 |
| 戝庫 |
|
岡嬍 |
| 亂杒戙堚愓弌搚亃 |
|
|
| 晉嶳巗偺撿惣晹偵偁傞奐儢媢屜扟嘨堚愓偱偼丄撽暥帪戙拞婜乮崱偐傜栺5000偐傜4500擭慜乯偺儉儔偑慡柺揑偵敪孈偝傟傑偟偨丅媢椝偺捀晹拞墰偵墌宍偺峀応傪愝偗丄偦偺廃埻傪傔偖傜偣傞傛偆偵孈棫拰寶暔丒扜寠廧嫃傪攝抲偟偰偄傑偟偨丅峀応撪偵偼偍曟傕偮偔傜傟丄側偐偵偼噫噙惢偺悅忺傝偑弌搚偟偨傕偺傕偁傝傑偟偨丅偙偺悅忺傝偼攋懝偟偨傕偺傪嵞壛岺偟偰嶌傜傟偨婱廳側傕偺偱偟偨丅 |

噫噙惢偺悅忺傝
亂奐儢媢屜扟嘨堚愓弌搚亃 |
|
| 僸僗僀傗噫噙偺嶻抧偼晉嶳導撪偵偼側偔丄僸僗僀偼怴妰導偐傜丄噫噙偼愮梩導偐傜傕偨傜偝傟偰偒偨傕偺偱偡丅婓彮側噫噙傗峝偄僸僗僀側偳偵帪娫傪偐偗偰寠傪偁偗偨忺傝嬍偼丄扤傕偑帩偰傞憰忺昳偱偼側偔丄儉儔偺側偐偺偛偔尷傜傟偨恖偑帩偰傞傕偺偱偟偨丅 |
| |
|