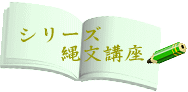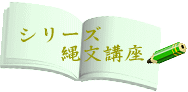| |
 貝塚から出土するもの 貝塚から出土するもの |
| 縄文時代の遺跡のひとつに貝塚があります。貝塚は、縄文人が捨てた貝殼が厚く堆積した場所です。貝塚では貝殻に合まれる石灰質の成分が有機物に付着すると腐りにくくなり、骨や歯などがよく残るようになります。貝塚では縄文人が食べた動物の骨、角や骨で作った骨角器のほか、埋葬された人骨が出土することもあります。富山市北代から呉羽町の丘陵のふもとには、小竹貝塚、蜆ヶ森貝塚など、シジミ貝を主体とした大きな貝塚があり、そこから多くの骨や骨角器が出土しています。 |
| |
 さまざまな骨角器 さまざまな骨角器 |
骨角器は、漁具などの生産用具と、おしゃれのために身につける装飾品に分けられます。漁具にはヤス・鈷・釣針などがあり、川や富山湾に出て魚を取っていました。小竹貝塚では、この漁具がたくさん出土しています。
また装飾品では、かんざしやペンダントがあります。それらは作り方も丁寧で、磨いてピカピカに光っています。イノシシの牙やサメの歯、変わったところでは幾何学形の穴があいたサメの脊椎骨に穴をあけてペンダントにしていました。ほかに、指輪状に加工したものまであり、縄文人がずいぶんおしゃれだったことがわかります。 |
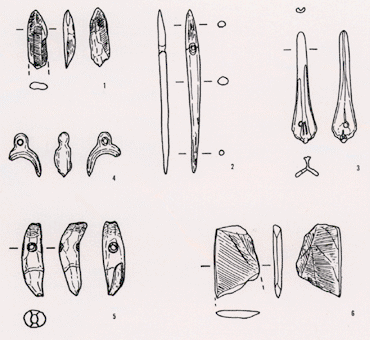
骨角器【小竹貝塚出土】 |
| |
 骨角器の材料 骨角器の材料 |
小竹貝塚からは、動物の骨の破片も多く出土しました。その中には人為的に叩き割ったり、一部を磨いたものもあります。これらは製作途中のものとみられます。
骨角器の材料には、多種多様な動物のさまざまな部位の骨が使われます。なかでも多いのはニホンシカとイノシシの足の骨です。まっすぐで、ヤスなど長い道具を作るためにちょうど良かったのでしょう。またシカの角でも釣針、鈷、かんざしなどを作っています。角は骨に比べると丈夫で、水に浸っても弾力があって折れにくいため釣針には適していたのです。 |
| |
 リサイクルの達人 リサイクルの達人 |
縄文人は、肉を食べるために狩をして動物を捕獲しますが、肉をきれいに食べてしまった後のかすもただ捨てることなく、骨角器を作ることで活用しリサイクルしていました。骨角器を製作する際には骨や角の特徴を熟知し、その性質をうまく利用していました。
自分たちの周囲にあるいかなるものも無駄にせず、工夫して生活していた縄文人たちは、まさにリサイクルの達人と言えますね。資源の大切さを忘れかけている私たち現代人も見習うことが必要なのかもしれません。 |
| |