呉羽三ツ塚古墳・呉羽三ツ塚遺跡は、富山市中心部から北西約4km離れた呉羽山丘陵北西部の台地上に位置し、周辺では最高所(標高約14m)に営まれています。
土地区画整理事業計画に伴い、平成15年11月から12月に試掘確認調査を行いました。 |
| |
| |
 呉羽山丘陵の首長墳 呉羽三ツ塚古墳 呉羽山丘陵の首長墳 呉羽三ツ塚古墳 |
呉羽山丘陵には弥生時代終末期(約1800年前)以降、古墳時代終末期(約1350年前)に至るまで地域首長の墳墓が数多く築かれています。呉羽三ツ塚古墳もその一つです。住宅建築や開墾などによって一部が削られており、これまでは13m×15m、高さ2.5mの方墳と推定されていました。
試掘確認調査の結果、本来の墳丘の大きさは15.5m×16.5m前後で、高さは約2mから2.3mであることがわかりました。ほぼ正方形の方墳と推定できます。墳丘は周溝を掘削した際に生じた土を約2mから2.3mの高さに盛って造成しています。
墳丘頂部に近い部分では良質の地山(明褐色ローム土)を使用し、表面をきれいに見せようとしています。墳丘上に葺石・埴輪・段築はないことも明らかになりました。 |
|
| |
|
古墳と周辺を区画するため、幅約2mから3mの周溝を墳丘の周りに巡らせていました。深いところでは1m以上の規模があります。周溝の外側で測ると古墳のエリアは約20m×23mとなります。
周溝内からは縄文土器などの遺物がわずかに出土しました。古墳の築造時期を決定づける土器は確認されていませんが、古墳の形から、古墳時代前期(約1700年前)のはじめに築かれたと推定されます。 |
 |
| 呉羽三ツ塚古墳の周溝 |
|
| |
| 当地域における地域王権の発生から展開過程を探る上で、今回の調査成果は重要な意味をもっています。 |
|
| |
| |
 奈良時代の集落跡 呉羽三ツ塚遺跡 奈良時代の集落跡 呉羽三ツ塚遺跡 |
| 呉羽三ツ塚古墳が立地する台地とは谷を挟んで西側に呉羽三ツ塚遺跡が所在します。 |
試掘確認調査の結果、奈良時代の溝や土坑、ピットなどがまとまって確認され、約5000平方メートルの面積で広がる奈良時代の集落跡であることがわかりました。
奈良時代の須恵器・土師器・鉄滓や中世の珠洲焼などが出土しています。鉄滓が出土していることから、鉄づくりをしていた可能性も考えられます。 |
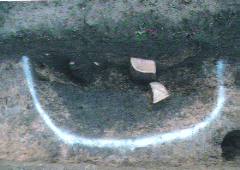 |
| 呉羽三ツ塚遺跡の土坑 |
|
|
| |
| |
| 関連書籍(表紙をクリックすると全国遺跡報告総覧のホームページが開きます) |
| |
 |
| |
富山市埋蔵文化財センター 2004
『富山市の遺跡物語 第5号』 |
|
|
 |